監査
内部監査は本当に意味がない?形骸化を脱却し価値を生む方法
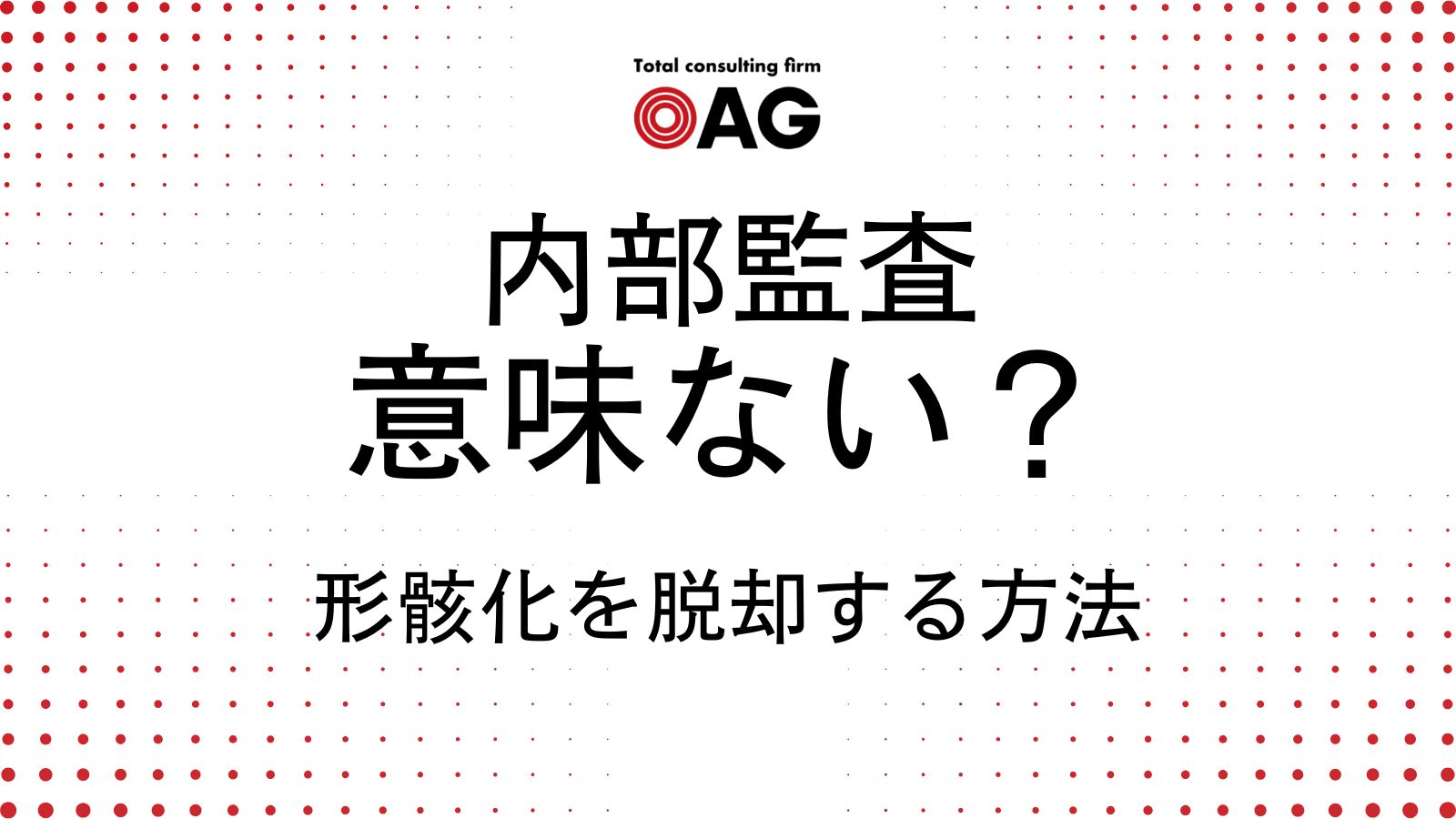
内部監査が「意味ない」「ただの形式」と言われることがあります。現場や経営層の温度差、形骸化した運用など、そう感じさせてしまう背景には理由があるのです。
本記事では、内部監査が形だけになってしまう要因と、その改善策について実践的な視点から解説します。
※そもそも内部監査とは何か、以下の記事でご紹介しています↓
内部監査とは?基本の役割・目的から手順まで徹底解説
Contents
内部監査は「意味がない」と言われるのはなぜか

企業のガバナンスやリスク管理において重要とされる内部監査ですが、現場や一部の経営層からは「意味がない」「形骸化している」といった声が少なくありません。なぜ、そのようなネガティブな評価がされるのでしょうか?
ここでは、内部監査は「意味がない」と言われる背景にある3つの主な要因を整理して解説します。
チェックリスト依存で実態を捉えきれないから
内部監査は「意味がない」と言われる要因のひとつは、チェックリストへの依存です。多くの企業では、内部監査項目が事前に整備されたリストに従って実施されますが、それが形骸化を招くこともあります。チェック項目をただ機械的に埋めるだけの内部監査では、現場の実態や潜在的なリスクを正しく捉えることができません。
たとえば、規程通りに書類が整っていても、実際の運用が伴っていなければ意味がありません。チェックリストに沿った内部監査では現場の実態や潜在的なリスクに気づけないこともあるのです。その結果、内部監査を受ける側は「また意味のない確認作業か」と感じ、内部監査そのものに対する信頼や期待が薄れていきます。
内部監査での指摘が改善につながらず効果が見えにくいから
内部監査で問題点を指摘しても、それ以降に具体的な改善が行われなければ、「結局なにも変わらない」と評価されてしまいます。現場からすれば、毎年同じような指摘を受けながらも実質的な改善がなされず、形式的な是正報告だけで終わる状況に疲弊してしまうのです。
また、改善活動が「言われたからとりあえず直す」といった表面的な対応で終わるケースも少なくありません。本来であれば、再発防止や業務効率の向上といった前向きな変化を促すのが内部監査の役割です。しかし、フォローアップが不十分だとその効果が見えづらく、社内からの信頼も得られにくくなります。
現場の手間ばかり増えコストパフォーマンスが悪いから
内部監査を受ける現場の担当者にとっては、内部監査への対応そのものが大きな負担になることがあります。事前の資料準備やヒアリング対応、指摘に対する是正報告の作成などは、日常業務とは別に追加で求められる対応です。
そうした手間をかけた割に、業務改善や効率化といった目に見える成果が実感できないと、「内部監査は時間と労力の無駄」と感じられてしまいます。とくに人員やリソースが限られている組織では、内部監査が「コスパの悪い作業」として捉えられがちです。その結果、内部監査そのものに対する協力意欲が低下し、形式的な対応に終始するという悪循環が生まれます。
内部監査が形骸化してしまう背景

内部監査が「意味がない」「形だけ」といった評価を受けるときは、企業の体制や関係者の意識に課題がある場合があります。
ここでは、内部監査が形骸化してしまう背景について、経営層・現場・内部監査部門それぞれの観点から見ていきましょう。
経営層の関心不足で儀式化しやすい
内部監査が組織内で形骸化してしまう原因のひとつが、経営層の無関心です。内部監査の報告を受けても実際の経営判断や改善につなげようとしない姿勢が見られると、社内全体にもその姿勢が伝わってしまいます。
たとえば、「内部監査対応は上場企業としての義務」程度にしか認識されていない場合、内部監査は単なるイベントになり、改善意識が育ちません。結果として内部監査人も「どうせ指摘しても何も変わらない」と感じるようになり、内部監査は実質的な機能を失っていきます。
現場の影響力が強く指摘事項が軽視される
内部監査が形骸化する要因のひとつに、現場の「受け流し」があります。内部監査の指摘を受けても、本気で改善に取り組まない、あるいは適当にやり過ごしていると、内部監査自体が軽視されてしまうのです。
現場側の影響力が強い企業文化では、内部監査部門が問題を指摘しても「現場がOKならそれでよし」となってしまい、改善の必要性が感じられなくなります。また、過去に是正してもしなくても特に評価やペナルティがなかった経験があると、形だけの対応が常態化してしまいます。
内部監査部門の人材・権限不足による影響力低下
内部監査部門の影響力が低下してしまう要因として、人材と権限の不足が挙げられます。多くの企業では、他部署との兼務や人事ローテーションによって内部監査業務に精通しない人材が配置され、専門性や継続性に欠けた内部監査になりがちです。
さらに、内部監査部門が経営層から独立しておらず、組織的に弱い立場にあると、いくら重大なリスクや改善点を指摘しても、経営層や現場から軽視されてしまうことがあります。こうした状況が続くと、内部監査の本来の目的が果たされず、「いても意味がない部門」と見なされる悪循環に陥ってしまいます。
内部監査が企業に必要とされる理由

内部監査に対して「意味がない」「形骸化している」といった否定的な見方がある一方で、多くの企業が内部監査を続けているのには明確な理由があります。
ここからは、内部監査が企業にとって必要な存在である理由を見ていきましょう。
不正・不祥事の防止とリスクの管理
企業活動における財務的なリスク、情報セキュリティリスク等の潜在的なリスクを早期に特定し、適切な予防策や対応策を講じることで、リスクを最小限に抑える役割を果たします。
また、社内の業務プロセスや財務状況を客観的に検証することで、不正行為や誤謬の発生を抑止し、もし発生した場合には早期に発見・是正することができます。
業務の有効性と効率性の向上
内部監査で社内のルールやマニュアルが適切に機能しているかを確認し、不備があれば改善を提案します。これにより、組織の管理体制が強化され、業務の健全性が保たれます。また、内部監査は無駄な作業や非効率な業務プロセスを発見し、改善を促すことで、組織全体の生産性向上に寄与します。
経営目標の達成支援と企業の信頼性向上
内部監査は、経営層から独立した客観的な立場で、組織の現状を分析・評価します。その結果を経営層に報告し、経営目標の達成に向けた具体的な改善策や助言を行うことで、意思決定をサポートします。
また、内部監査を通じて企業が健全で透明性の高い経営を行っていることを内外に示すことができます。これにより、株主や取引先、顧客、社会全体からの信頼が高まり、企業の持続的な成長を支えます。
内部監査を「意味のある」ものにするための改善策

内部監査は「意味がない」と感じられてしまう背景には、複数の要因が絡んでいます。しかし、こうした問題は適切な改善策を講じることで解消することができます。
ここでは、内部監査を「意味のある活動」へと変えていくために、組織全体で取り組むべき具体的な改善アプローチを見ていきましょう。
経営層を巻き込み目標を共有する
内部監査を形骸化させないためには、経営層を巻き込むことが不可欠です。内部監査を「上場維持のための義務」や「形式的なチェック」と捉えるのではなく、経営課題の発見や意思決定の材料として活用する姿勢が求められます。
経営トップ自らが内部監査報告を受け止め、必要に応じて改善策に予算や人材を投じることで、現場にも「この取り組みは本気だ」というメッセージが伝わるでしょう。
現場との信頼関係を築き協働する
内部監査を成功させるには、現場との信頼関係づくりが欠かせません。現場から内部監査が「ミスを探すための活動」と見なされているうちは、内部監査に対する不信感から協力も得にくくなります。
しかし、業務実態を理解したうえで「どうすればより良くできるか」を一緒に考える姿勢を示せば、内部監査人は「敵」ではなく「伴走者」として受け入れられるはずです。内部監査部門と現場が対話を重ね、改善に向けた協働関係を築くことで、内部監査の質も結果も大きく変わっていきます。
内部監査人の専門性と提案力を高める
内部監査の質を高めるには、内部監査人自身の専門性と提案力の向上が不可欠です。業務や業界に関する理解が浅いままだと、どうしても形式的なチェックや机上の指摘にとどまり、現場から「的外れ」と受け取られてしまうこともあります。
一方で、内部監査人が実務に即した改善提案を行えるようになれば、現場からの信頼は大きく変わります。資格取得や他部署とのローテーションなどを通じて知識と視野を広げることで、内部監査部門は「チェック機関」から「価値あるアドバイザー」へと進化していくのです。
※内部監査人の教育については、以下の記事でもご紹介しています↓
現場力が上がる内部監査人の教育法とは?社内研修のポイントやコツも解説
指摘後のフォローアップで実効性を確保する
内部監査の本当の価値は、指摘後の「その後の変化」を生み出せるかどうかにかかっています。指摘するだけで終わってしまえば、改善されないまま放置される可能性があり、内部監査の意味も薄れてしまいます。
だからこそ、フォローアップの仕組みが重要です。たとえば、改善項目ごとに担当者と期限を明確にした進捗管理を行い、定期的にレビューする体制を整えることで、改善への意識を持続できます。
まとめ:内部監査を価値あるものにしよう

内部監査は、経営の質を高め、組織全体の改善を促す重要な機能です。経営層の関与、現場との協働、内部監査人のスキルアップ、そして確実なフォローアップによって、「意味のある」内部監査へと進化させることができます。
OAGビジコムでは、内部監査のアウトソーシングや内部監査の体制構築支援を通じて、企業が実効性の高い内部監査を行えるようサポートしています。「内部監査が形骸化している気がする」「社内リソースが足りず困っている」「初めて内部監査体制を整える」といったお悩みをお持ちのご担当者様は、ぜひお気軽にご相談ください。




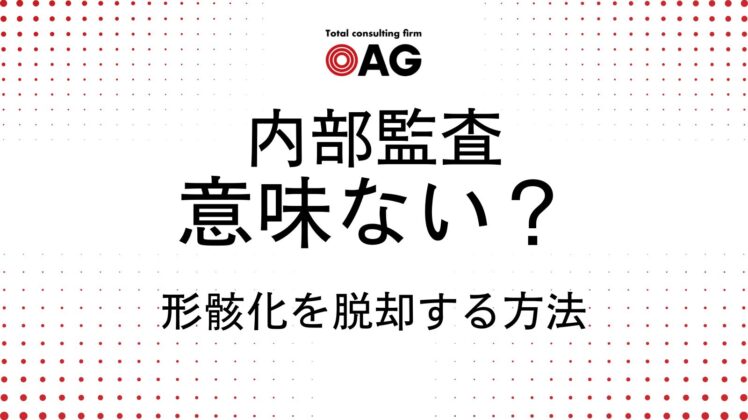
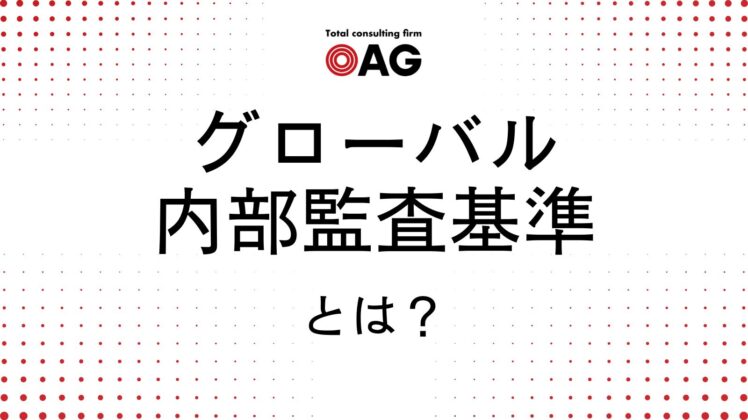

必要に応じて経営層への報告に繋げるなど、実行まで見届ける仕組みがあってこそ、内部監査は初めて「意味ある活動」と言えるのです。