監査
グローバル内部監査基準とは?概要と企業の対応策を解説!
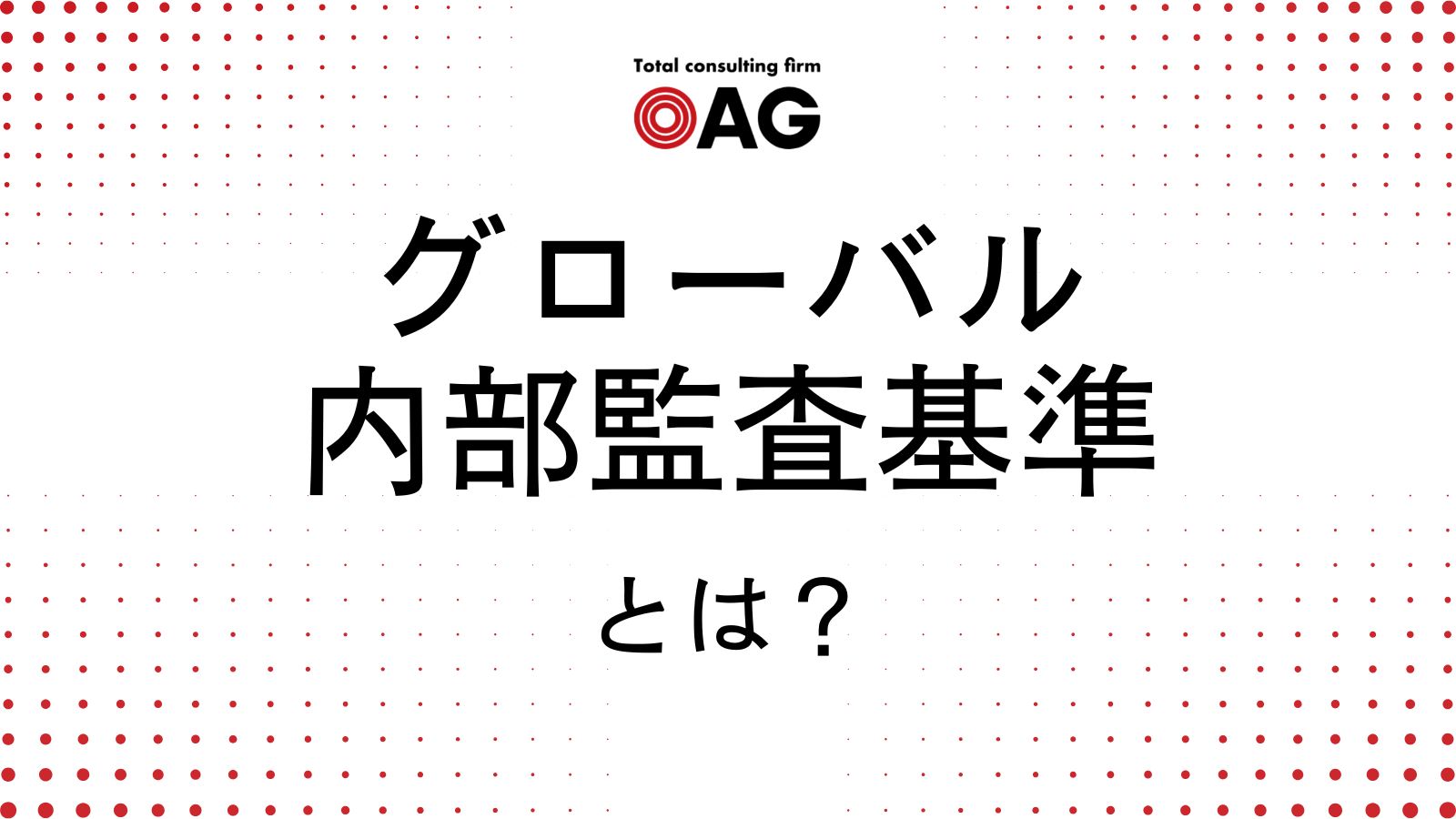
内部監査の「専門職的実施の国際フレームワーク(International Professional Practices Framework 以下、IPPF)」は、内部監査人協会(IIA)が公表した権威ある知識体系を整理したものです。IPPFの改訂に伴い、2024年1月に「グローバル内部監査基準」が公表されました。新基準は2025年1月9日に施行されています。
Contents
専門職的実施の国際フレームワーク(IPPF)の構成

新「IPPF」は、「グローバル内部監査基準」・「トピック別要求事項」・「グローバル・ガイダンス」によって構成され、「グローバル・ガイダンス」以外は必須事項です。
必須事項
▶グローバル内部監査基準
内部監査の世界的な専門職的実施の指針であり、内部監査部門の品質を評価、向上させる基礎となります。
▶トピック別要求事項
特定の監査対象に関する内部監査業務の一貫性と品質を向上させ、そのようなリスク領域で個々の内部監査業務を行う内部監査人を支援することを目的としています。内部監査人は、個々の内部監査業務の範囲にここで特定されたトピックのいずれかが含まれる場合、関連する要求事項に適合しなければなりません。
補足的事項
▶グローバル・ガイダンス
内部監査業務を実施するために、必須ではない情報、助言及びベストプラクティスを提供することにより、「グローバル内部監査基準」を支援するものです。
「グローバル内部監査基準」とは

「グローバル内部監査基準」の中核をなすのは、有効な内部監査を可能にする15の指導的な原則です。各原則は、要求事項、実施にあたって考慮すべき事項、および適合していることの証拠の例を含む複数の基準によって支えられています。
これらの要素が一体となって、内部監査人が原則を達成し、「内部監査の目的」を果たすことを支援しています。
「グローバル内部監査基準」の構成
「グローバル内部監査基準」は、以下の5つのドメインと15の指導的な原則で構成されています。
ドメインⅠ 内部監査の目的
ドメインⅡ 倫理と専門職としての気質
原則1 誠実性の発揮
原則2 客観性の維持
原則3 専門的能力の発揮
原則4 専門職としての正当な注意の発揮
原則5 秘密の保持
ドメインⅢ 内部監査部門に対するガバナンス
原則6 取締役会による承認
原則7 独立した位置づけ
原則8 取締役会による監督
ドメインⅣ 内部監査部門の管理
原則9 戦略的な計画策定
原則10 監査資源の管理
原則11 効果的なコミュニケーション
原則12 品質の向上
ドメインⅤ 内部監査業務の実施
原則13 個々の内部監査業務の計画の効果的な策定
原則14 個々の内部監査業務の実施
原則15 個々の内部監査業務の結論のコミュニケーション及び改善措置の計画のモニタリング
ドメインⅡからⅤには、以下の要素が含まれます。
- 原則:関連する要求事項及び考慮すべき事項をおおまかに記述したもの
- 基準:以下の事項を含むもの
▶ 要求事項:内部監査のための必須の実務
▶ 実施に当たって考慮すべき事項:要求事項を実施する際に考慮すべき、一般的で望ましい実務
▶ 適合していることの証拠の例:「グローバル内部監査基準」の要求事項を実施していることを示す方法
「要求事項」の項では、「~しなければならない(must)」という明確な義務表現で、準拠の基準が記されています。
「実施に当たって考慮すべき事項」の項では、一般的かつ望ましい実務を示すために「~すべきである(should)」や「~してもよい/することがある(may)」という言葉を使っています。
IPPFの改訂

IPPFは、前回2017年に改訂されており、2024年改定は7年ぶりです。今回の改定は、世界中の実務家やステークホルダーからの質の高い内部監査へのニーズに応え、責任を果たせるようにすること、現在の内部監査のトレンドに照らした実務に対応することが狙いとされています。
重要な変更点
- IPPFの構成を簡素化
- 6つの構成要素(「使命」、「定義」、「倫理綱要」、「基本原則」、「基準」、「実施ガイダンス」)を新しい「基準」にまとめた
- 新しい「基準」の中に新しい「内部監査の目的」を設けた
- 専門職としての正当な注意を加えることで「倫理と専門職としての気質」を充実させた
- 各「基準」の後に「適合していることの証拠」を加えた
- 公共セクター、小規模内部監査部門、およびアドバイザリー業務に関する相違点を加えた
- 内部監査部門と様々な活動に対する内部監査部門長と内部監査人との役割を明確にした
- 品質のアシュアランスと改善のプログラムについて、遵守が義務付けられる要求事項として整理され、これにより、すべての内部監査部門が内部監査の品質を評価し、継続的に改善するプログラムを策定・実施することが必須の義務となった
「グローバル内部監査基準」への対応ステップ

IPPFの改定を受けて、内部監査部門がとるグローバル内部監査基準への対応は以下の3ステップで進めることができます。
ステップ1:現状とのギャップを分析する
まず、自社の内部監査規程や実務が、グローバル内部監査基準の要求事項とどのくらい異なっているかを洗い出します。特に、取締役会の役割、負託事項の明確化、そして品質のアシュアランスと改善のプログラムに関する要求事項等の新基準の重要な変更点に焦点を当てて、現状との乖離を特定します。この段階では、単なる文書の比較だけでなく、実際の監査プロセスや報告体制も対象とします。
ステップ2:規程の改訂と運用の準備を行う
ギャップ分析の結果に基づき、既存の内部監査規程を改訂し、グローバル内部監査基準に準拠した内容に更新します。特に、内部監査の目的、「グローバル内部監査基準」を遵守することへのコミットメント、負託事項及び組織上の位置付けと指示・報告関係を明確に記述します。同時に、新しい規程に沿った監査計画や報告書の様式を策定するなど、運用面での準備も進めます。必要に応じて、内部監査人に対する研修を実施し、新たな基準への理解を深めることも重要です。
ステップ3:新基準に沿った監査を実践し、継続的に改善する
改訂した規程に基づき、実際の監査業務を開始します。この際、単に形式を守るだけでなく、リスクベースの考え方や、コンサルティング業務の提供も視野に入れます。そして、監査活動を通じて得られた知見を活かし、定期的に品質のアシュアランスと改善のプログラムを実施することで、内部監査の品質を継続的に評価・改善していきます。これにより、グローバル内部監査基準への準拠を一時的なものに終わらせず、組織のガバナンス強化に持続的に貢献する体制を構築できます。
まとめ:グローバル内部監査基準を自社の成長に活かそう
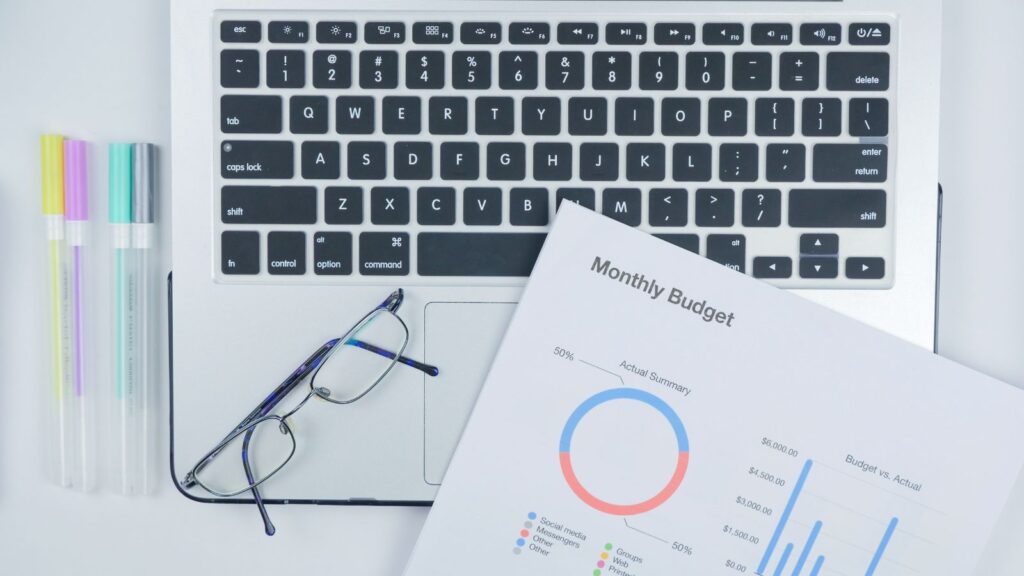
グローバル内部監査基準(GIAS)は、内部監査を通じて企業の信頼性と競争力を高めるためのフレームワークです。義務ではないとはいえ、企業が継続的に成長し、ステークホルダーからの信頼を確保するには、この基準を自社の内部監査体制にどう活かすかが重要な視点となります。
OAGビジコムでは、グローバル内部監査基準への対応を含めた内部監査業務の支援・アウトソーシングを承っております。ご相談は無料で、課題の整理から現場での実装支援まで、経験豊富な専門家が丁寧に対応します。
「専門知識が社内にない」「今の内部監査体制では新基準に対応しきれない」などのお悩みをお持ちのご担当者様は、どうぞお気軽にOAGビジコムまでご相談ください。




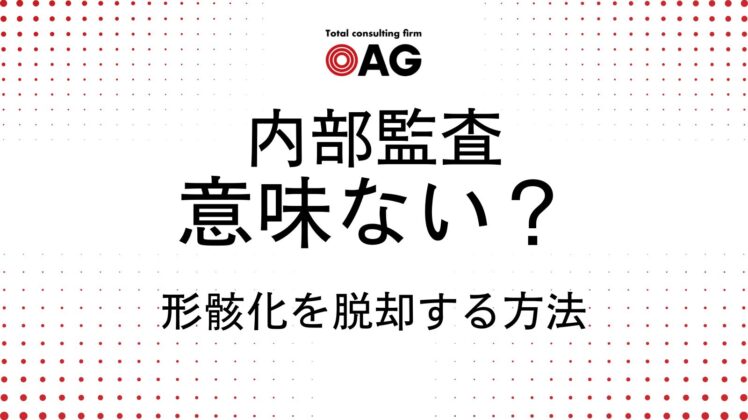
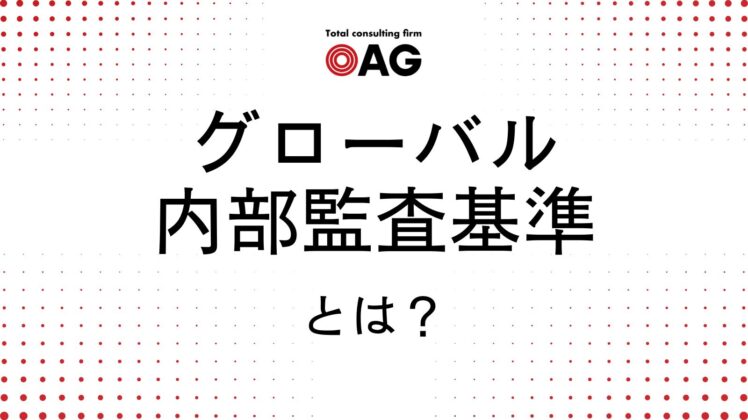

TEL:06-6310-3101