監査
現場力が上がる内部監査人の教育法とは?社内研修のポイントやコツも解説
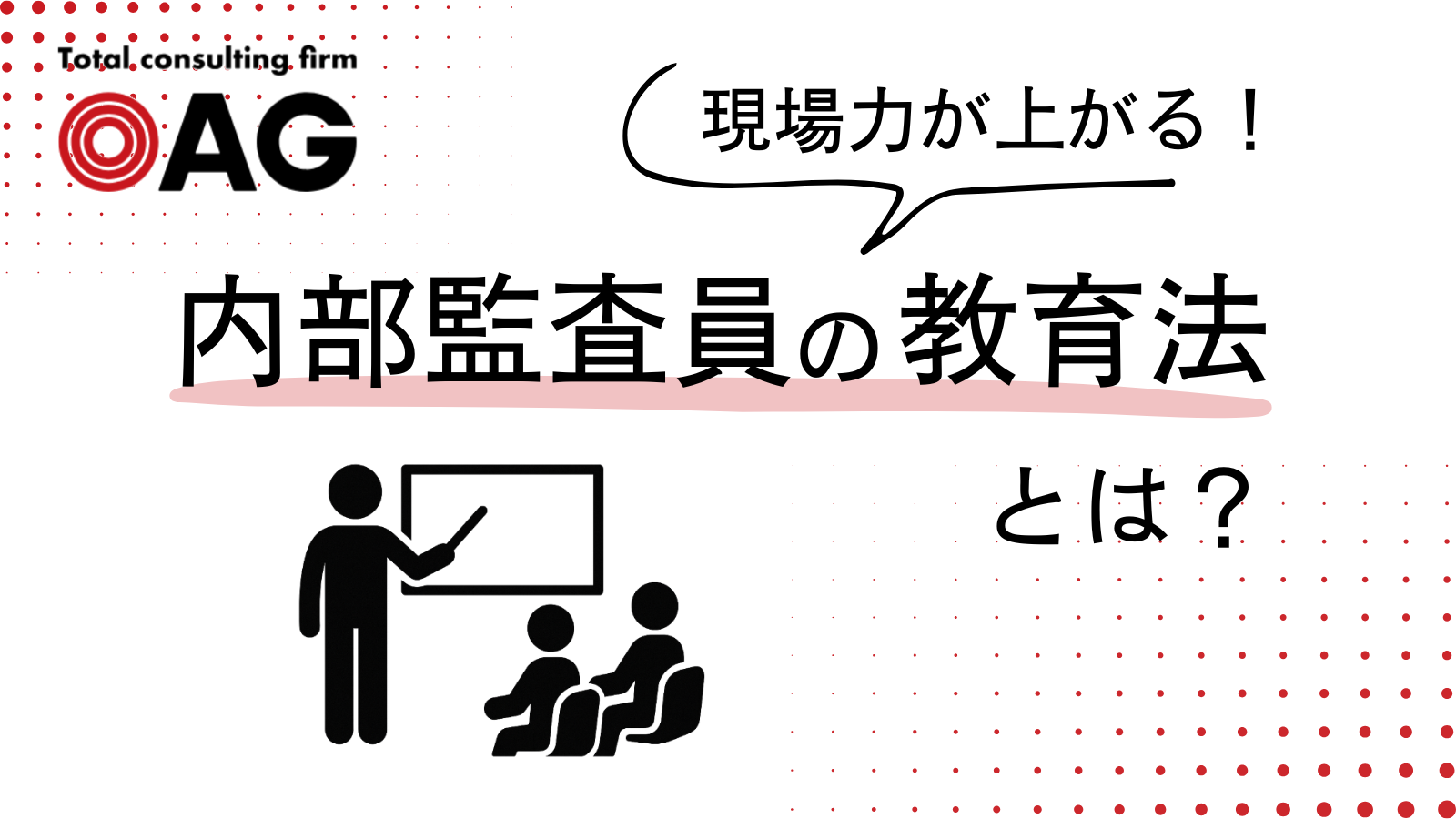
内部監査人の教育に取り組んでも、「現場が変わらない」「内部監査が形だけで終わってしまう」と悩む企業は少なくありません。
本記事では、実際に「現場で活きる内部監査人」をどう育てるか、教育手法の選び方や定着のポイント、外部活用のメリット・デメリットまで徹底解説します。「どの方法が自社に合うのか」とお悩みのご担当者様も、ぜひ参考にしてみてください。
Contents
なぜ内部監査人の教育が必要なのか?

内部監査は単なる「チェック業務」ではなく、業務の適正性を確認し、組織全体の品質やリスク管理レベルを高める重要な仕組みです。内部監査人がその役割を果たすためには、適切な知識とスキルを備えた人材の育成が欠かせません。
まずは、教育の意義について、2つの観点から見ていきましょう。
社内ルールの理解で現場力を高める
内部監査人が会社の規程やマニュアルを正しく理解していなければ、現場との認識ズレを引き起こします。内部監査の場で「これはルール違反なのか?」「実務として許容されるのか?」といった曖昧さがあると、指摘の信頼性が低下します。
そのため、内部監査人は社内ルールの教育を通じて、社内のルール・業務フローを体系的に理解する必要があるのです。現場と同じ目線で会話できる力を養うことが、内部監査の質を大きく左右します。
内部監査の質向上で組織全体を強化する
質の高い内部監査が行われると、不適合の早期発見や業務改善の機会が得られ、結果的に組織全体の生産性やリスク対応力が高まります。内部監査人の教育が不十分だと、形だけの内部監査になってしまい、改善にもつながりません。
内部監査人の育成は、企業の品質・業務改革力を底上げする「経営投資」として捉えることが重要です。
社内で育成するか、外部に任せるか?内部監査人教育の3つの方法

内部監査人をどのように育てるかは、企業の体制や人材リソースによって異なります。コストや即効性、業務理解度などのバランスを踏まえて、自社にとって最適な教育手段を選ぶことが重要です。
ここでは3つの代表的な方法と、それぞれの特長を紹介します。
社内研修のメリット・デメリット
社内で完結する研修には、自社のルールや文化を反映しやすいため、受講者が実務とのつながりをイメージしやすくなるのがメリットです。コストも抑えられ、必要なタイミングで柔軟に実施できます。
ただし、講師役の育成や教材整備に負担がかかりがちで、属人的になったり、教育効果が定着しにくいリスクもあります。社内のリソースですべてまかなう体制には限界があり、相応の工数と改善努力が必要です。
外部セミナー活用のメリット・デメリット
外部主催のセミナーは、ISOや内部監査の専門知識を体系的に学べるだけでなく、他社事例や最新トレンドにも触れられるのが大きな魅力です。学習効果も高く、初心者の導入に向いています。
一方で、自社固有の課題には踏み込めず、受講後にどう実務に落とし込むかが課題となります。また、開催地や日程の都合により、参加ハードルが上がるケースも否めません。
外部講師招へい(アウトソーシング)のメリット・デメリット
企業ごとの実情を事前に把握したプロの講師から直接指導を受けられるのが、外部講師招へい型(アウトソーシング)の強みです。現場に即した模擬監査やケース演習を通じて、即戦力の内部監査人を育てることができます。
ただし、社内研修や外部セミナーへの参加よりはコストが高めで、教育内容のカスタマイズや打ち合わせには準備が必要です。
内部監査人に求められる知識・スキル・適性とは?

内部監査人に求められるのは、社内規程などの知識だけではありません。内部監査の現場では、文書や会話から課題を読み取る観察力、正しく伝える表現力、現場と信頼関係を築く人間力など、複合的な資質が問われます。
ここでは、内部監査人に求められる知識・スキル・適性を見ていきましょう。
内部監査人が知っておきたい基礎知識
内部監査に携わるうえで、ISO9001など該当する規格の要求事項を理解しておくことは必須です。加えて、自社の業務マニュアルやプロセス構造も押さえておくことで、実務に根差した有効な内部監査が可能になります。
また、内部監査の一連の流れ(計画→実施→報告→フォローアップ)を体系的に理解しておくことも重要です。
内部監査の流れについては、以下の記事で詳しく紹介しています。
内部監査とは?基本の役割・目的から手順まで徹底解説
内部監査で求められるスキル
内部監査における現場ヒアリングでは、以下のようなスキルが必要になります。
・質問力
・観察力
・言語化能力
・伝達力
相手の話を引き出す「質問力」や、事実と意見を整理する「観察力」は特に重要なスキルです。さらに、発見事項をわかりやすく文書化する「言語化能力」、監査結果を関係者に納得感をもって伝える「伝達力」も欠かせません。
内部監査人に向いているのはこんな人
内部監査は相手の非を指摘する場ではなく、改善のきっかけをつくる建設的な活動です。そのため、人の話を冷静に聞ける傾聴力や、柔軟に対応できるバランス感覚がある人には特に向いています。
また、業務への興味や向上心を持ち、継続的に学ぶ姿勢がある人ほど、内部監査人としての成長が早い傾向があります。社内の物事を経営視点で確認できる人も、内部監査人に向いているといえるでしょう。
効果的な内部監査人教育プログラムとは?
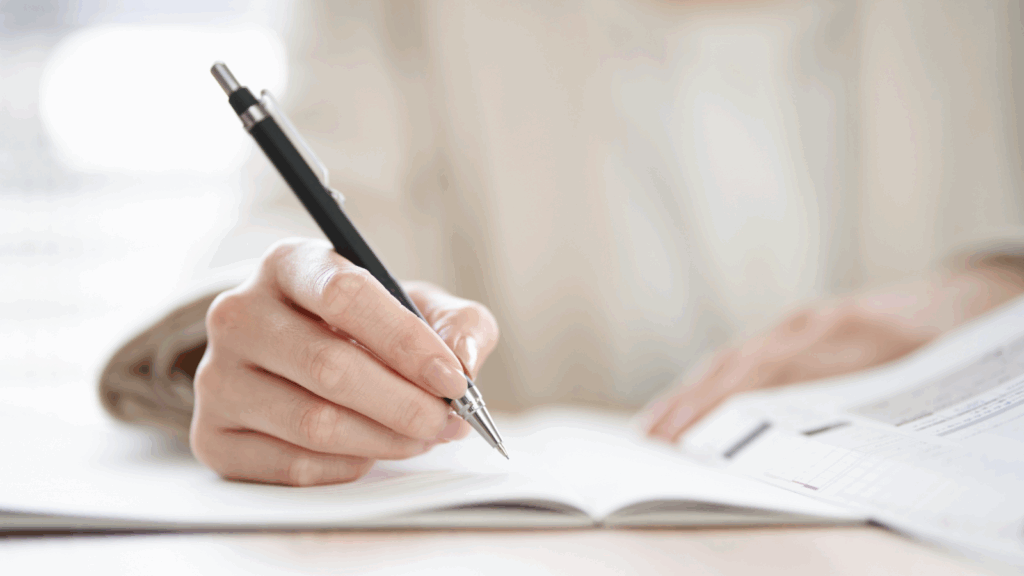
どのような教育プログラムを設計するかによって、内部監査人の質は大きく左右されます。知識の習得だけでなく、実践的な体験を通じて「使えるスキル」を身につけることがポイントです。
ここでは、効果的な内部監査を実施できる人材を育てるための代表的な教育要素を、3つご紹介します。
社内規程や業務内容を反映した研修
定型的な内容ではなく、自社の実情に即した教育こそが実効性を高めます。たとえば、実際に使っているマニュアルや記録を教材として活用することで、受講者が「自分事」として理解できるようになります。
また、過去の指摘事例を振り返ることで、具体的な内部監査人としての着眼点を学ぶこともできます。
模擬監査(ロールプレイ)の導入
知識を学ぶだけでなく、実際の内部監査がどのようなものなのかを模擬的に体験することが、スキルの定着に効果的です。ペアになってインタビューやチェックリスト記入を行い、フィードバックを受けることで、自身の課題に気づき、改善できます。
初めての内部監査人でも、「現場でどう動けばいいか」がイメージしやすくなります。この「イメージしやすくなる」ということが、教育においてとても重要なポイントです。
OJT(実地研修)の活用
ベテランの内部監査人と一緒に現場を回り、実際の内部監査に同行するOJTは、もっとも実践的な育成方法です。経験豊富な先輩から質問の仕方や現場対応を直接学ぶことで、教科書では得られない「生きた知識」が身につきます。
研修後すぐに単独で動くのではなく、段階的に経験を積ませることで自信と実力を育てていきましょう。
研修後、内部監査人をさらに成長させるには?

初期研修やOJTを経て内部監査の基本を習得した後も、継続的なスキルアップと実務経験の蓄積が欠かせません。内部監査人として成長を続けるには、組織として「学びの機会」と「実践の場」を定期的に用意することが重要です。
ここでは、内部監査人の成長を加速させる2つの取り組みを紹介します。
より多くの実践経験を積む
内部監査のスキルは、実際に現場を見て、話を聞き、記録を確認し、指摘をまとめる…というように、場数を踏むことによって磨かれていきます。
年に数回しか内部監査の機会がない場合、経験不足で自信を持てない内部監査人が多くなるのも無理はありません。年次計画に基づいて内部監査を多数行うことで、自然と判断力や着眼点が養われ、報告書の質も向上します。
社内勉強会・情報共有の場を設ける
内部監査人同士で内部監査結果や気づきを共有する勉強会は、実務知識の相互補完に効果的です。他の内部監査人の視点やアプローチに触れることで、自分の内部監査の幅が広がります。
また、最近の指摘事例を定期的に振り返る場を設ければ、内部監査の質の底上げにもつながります。ツールやポータルで情報を蓄積・共有できるような仕組み化を行うこともおすすめです。
まとめ:自社に合った方法で内部監査人を育成しよう

内部監査人の育成は、単なるスキル付与ではなく、企業の品質や改善文化を支える「仕組みづくり」の一環です。社内研修、外部活用、OJTなどの方法は、それぞれの強みと制約を理解したうえで、自社に合う組み合わせを選ぶことが大切です。継続的な学びと実践の場を設計し、「内部監査を通じて現場と組織を強くする」人材を育てていきましょう。
OAGビジコムでは、内部監査のアウトソーシングに加え、内部監査人の育成支援も行っております。業務に即したOJTや集合研修を通じて、内部監査のスキルだけでなく、リスク管理意識や改善視点も同時に高め、貴社内で継続的に「自走できる」体制づくりを支援いたします。
「内部監査体制を強化したいが、人材育成に不安がある」「実務に活かせる内部監査スキルを社員に身につけさせたい」とお考えのご担当者様は、ぜひ一度OAGビジコムへご相談ください。




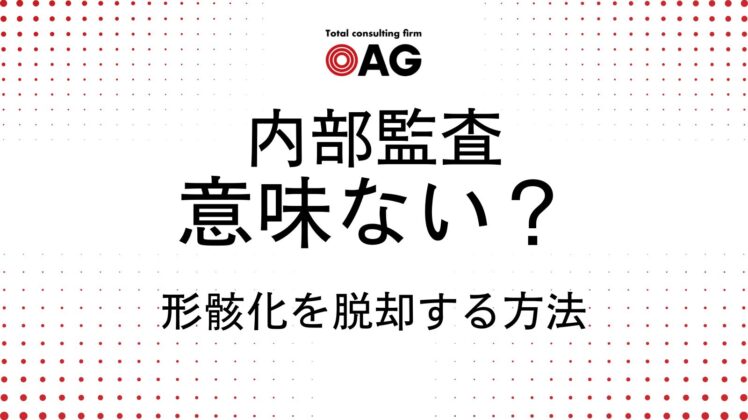
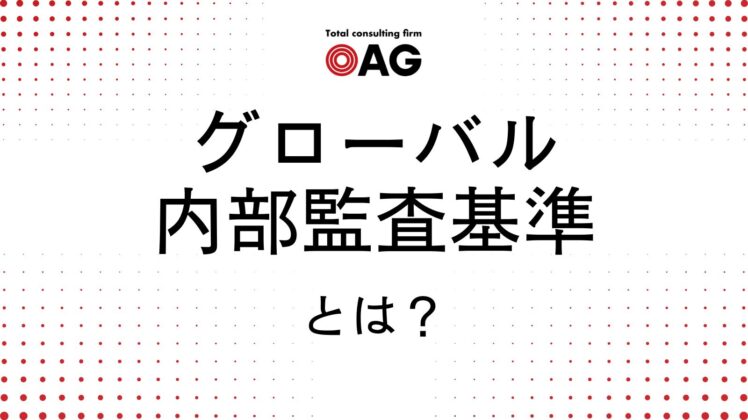

外部講師による内部監査人研修は、特に教育設計が不十分な企業にとって有効な選択肢です。講義と模擬監査を組み合わせた実践型のプログラムを実施することで、内部監査記録の記述精度や現場での質問力が向上するケースが多く見られます。